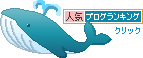流れ島流離譚 11
自分の住む世界のすべてを客観的に見通したければ高いところへのぼればいい。町外れの丘、町で一番高い塔。そんなものがなければ、飛行機に乗るなり、翼をつけてジャンプするなりどうにかして。
確かそんなことを鼻侯爵が言っていた。
「ジャンプするっていうのは、無理があるな」
思わず口に出せば、
「ほほう、飛び降りますか、ここから」
と、とんちんかんな答えをくれるのはもちろんシマナガシで、約束通りお茶を入れてもらい、いつしか語り合っている。
窓の外は笑ってしまうような景色である。「絵葉書のような」という表現があるが、絵葉書の絶景を真似て子供が7色くらいのクレヨンで描いたような、異様に鮮やかな景色がここにある。青緑色の色合いを微妙に変えながら水平線まで続く海、そのぼやけた境界から湧き出す雲を纏った空。それらを遠景に、この島のくっきりとした陰影のある青い森、白茶色の崖、白亜の砂浜。そしてこの部屋は、テーブルといい椅子といい、目に入る調度のほとんどが、ガラスだろうか、無色透明にできている。透き通ったティーポットから透き通ったカップに注がれた薄黄色のお茶をごくりと飲む。初夏の花の香りがする。
「高いところに、ねえ。そうとも言えるしそうでないとも言えましょう。低いところへ行ってもよければ、高くも低くもないところもまたよし。そうですよねえ」
シマナガシの意味不明の相槌は鼻侯爵の不敵に謎めかせた話し方を思わせて、今の今まで忘れていた記憶の断片が次々と顔を出して私を混乱させる。
「そうだ、でも、高いところへのぼればそれでいいと思ってはいけない、とも言っていた」
「ほほう」
「高いところからはたくさんのものが見えるけれど、たとえば入ったことのない隣家の風呂場からの眺めを知ることはできない。自分の家の窓から見えるもの以外はほとんど見えはしない、ただほんの少しずつすべてがずれて見えるその眺めがどんな感覚をもたらすか、町を俯瞰したくらいで決してわかりはしない。確か、そんなようなことを」
「なるほど、やっぱりね。そんな単純なやつじゃないと思いましたよ、ハナチャンは」
シマナガシは満足そうに顎を撫でている。さっきから、何も言っていないに等しい適当なことばかり言うのだから、少々腹も立ってこようというものだが、
「いやなに、実に初歩的な推理をしただけですよ」
と、何を誤解したのかまたホームズ気取りなのである。
「つかぬことを聞くけれど、猫って肩、凝る?」
突然話題を変えてみると、シマナガシは丸い翡翠のような目をさらに大きく見開き、ぱちぱちと瞬きをした。

焼いて食う

「いっそのことあいつ、焼いて食ってやろうと思うんだ。腹立つから」
「何の話」
「だからあいつだって、シノブ」
人をバーベキューに誘うなり、冬実は物騒なことを言う。
「さすがに丸ごと焼くと気味が悪いし、だいたいみんなにバレちゃうでしょ。まずはバラバラにしないとな。ねえ、手伝ってよ」
「いやだよ」
夏に生まれたのに冬実とは、両親が冬の情緒を愛してつけた名前なのだろうが、やはり生まれた季節は体を表すのか。その名との、しみじみするほどの違和感が、長く付き合っても毎度抜けないのがこの冬実という人だ。午睡の後にわざわざ熱いお茶を飲むような、気だるい夏が似合う。海へ行こう、水着になろう、ビールがうまい、という夏では、ない。今日もタンクトップを長くしたようなワンピースの上に羽織った半袖のシャツが、左右非対称に着崩れているのが不思議と様になっている。そんな冬実がバーベキューとはらしくないが、間々田君の発案だと聞けば、合点が行くような、行かないような、少なくとも冬実が言い出したのでないことには納得できる。
冬実が腹を立てているシノブ君とは、私たちよりだいぶ年下の男の子だった。じゃれつくのがうまいけれどべたべたしない、気まぐれだけれど、振り返れば定位置で何食わぬ顔で待っている。そんな、猫のような子だ。冬実がシノブ君に、ちょっとした「道ならぬ」思いを抱いていることに気づかないではなかったが、その思いが一方通行なのか、密かに両方向に開通しているのか、どうも後者に思えるのが危うい。「道ならぬ」恋になる他ないのは、冬実にれっきとした恋人がいるからで、それが間々田君なのだった。あからさまに気づいた人がいなさそうなら黙っておく、誰にも、もちろん冬実にも。それが今のところの私の見解である。
間々田君にもバーベキューは似合わない。いつもニコニコしていて、真面目で、いい人だが、バーベキューは似合わない。真面目すぎて、何を話して良いのだか、よくわからなくなる人だ。だが、天気の話に始まり、最近見た映画、流行っている変な言葉、新世代のスマホに搭載されるらしい機能、などなど、絶妙に当たり障りのない話題の引き出しが豊富なので、流されていれば「楽しく会話した」ことになってくれる。実にいい人だ。
「間々田君の高校の友達に、バーベキュー名人がいるらしくて」
「名人?火をおこすとかそういうの」
「わかんないけど、バーベキュー奉行みたいな人だって。その人が一緒にやろうっていうから、来てよ」
「いいけど、どこで、何人くらいでやるの」
「ほら昔、急に凧揚げしたくなって行ったあの公園、バーベキュー場があるらしくて。その名人と、もう一人同級生の男の子が来るって」
「じゃあ、女の子呼んでこいってことなの」
「別に、なんでもいいんじゃない」
「そうは言っても期待してるかも。牧野呼ぼうか」
「うん、任せる」
冬実にありがちなことではあるが、遊びの計画を立てているというというのに、鬱々と沈んだ声で話す。かと思えば、いっそ焼いて食おうかと来るのである。
冬実と間々田君とは結婚の約束をしているという噂があった。むしろ、「結婚だとかそういう形にはこだわらず、一緒にいようよ」とか何とか大真面目に言いそうだというのが私が間々田君に持つイメージだが、冬実が別れたいといえば、彼はぐずぐずと未練を見せたりはしないのではないだろうか。「冬実ちゃんがそうしたいなら、しょうがない」そんなふうに、まっすぐな目で、言うのではないか。
平日の昼間のファミレスで、偶然冬実とシノブ君を見かけた。そっと離れた席に座り、声はかけなかった。シノブ君の前には、ドリンクバーのありとあらゆるお茶の残骸が並び、冬実はコーヒーを飲んでいた。二人は黙りがちで、だが時々爆発的に笑った。あれは何杯目のコーヒーだったのだろう。
冬実には、自分なりの誠意だか仁義のようなものを、人に対して頑なに通すところがあった。だがそれは隠された顔で、見える部分はとにかくとらえどころがなく、恋人の選び方はいつも実にいいかげんだ。そうして選んだ前の恋人に飽きていたところへ、折良く間々田君が現れた、そんなことだと思う。続けて現れたシノブ君には、しかし折など良かろうが悪かろうが、冬実の心を捉えたに違いないと、私にまで確信させる何かがあった。
冬実、今までの、投げやりな恋のつけだよ。ここいらで、ちゃんと清算すればいい。
「マグロ解体ショーなら見たことあるんだけど。あと、あんこうの吊るし切り。どっちにしてもよく覚えてないなあ」
「やわな刃物じゃだめだろうよ。出刃包丁、持ってる?」
「ないな。買わなきゃ。あ、でも間々田君持ってたかも」
「不法な使い方をするんだから、そこは自分で買いなよ」
「それもそうだ」
真面目にひとつひとつ話をすれば、きっと間々田君はわかってくれる。だが「真面目に話をする」というのは間々田君の流儀である。それは世間でいう正義にも近いが、合わせることに疲れる人もいることに、彼は気づかない。思うに、冬実は疲れていたのだ。無理に人に合わせるタイプではないが、冬実の全身で発する音のない言葉を、彼が解さなければ、日本語を話せる以上、冬実の方が合わせた形になるのは、仕方のないことだ。知らず間々田君の流儀に合わせていたことにも、別れの手続きすらその流儀に従わねばならないことにも、それらすべてが苦痛であるにも関わらず、彼を選んできた自分自身にも、疲れていたのではないだろうか。そして彼女の発する「言葉」をすらすらと当たり前に解読する人と出会ってしまっては、その疲れを看過するのが難しくなった。というのは、私の推測に過ぎないのだが。
バーベキューの日、冬実はぎょっとするほど大きく重たいキャリーケースを引きずってきた。
「おっ、すごいね、何が入ってるの?」
バーベキュー奉行が、すかさず聞いた。
「後で焼いて食べようかと思って。でもまだ秘密」
「えー、何だろう。馬まるごと一頭くらい、入ってそうだよなあ」
「まさか、馬ってでかいよ、見たことないの」
皆楽しそうだった。奉行の終始上の機嫌も、思えば冬実の大荷物に端を発したものだった。
冬実はすぐに酔ってビールと缶酎ハイを混ぜはじめ、間々田君はまずいまずい、何をするんだと、珍しくはしゃいで飲んでいた。
まだまだ宴が続くと思われた頃、
「なんだか私、お腹がいっぱいですっかり満足して眠くなっちゃった。だからこれ、焼いて食べようかと思ったけど、持って帰るわ」
突然冬実が言い出した。
じゃあ送っていくよ、くらいのことを言えばいいのに、そういう気が利かないのが間々田君で、「気をつけてね」という一言を背に、冬実は一人、ずんずんと去って行った。
何に気をつけろというのか、気をつけないといけないのは自分だろう、私は救い難くあきれた気持ちで彼を見ていた。伊達に言外のニュアンスをたっぷりこめて「いい人」と言われがちなわけではない。キャスターをつけて転がしているのに、冬実の荷物はひどく重そうだった。
トイレに立った時に冬実に電話した。電波が悪く、今時珍しいほどひどく混線していた。
「私、どうせきっとすぐに別れちゃうと思うんだよ。だけどね」
それが間々田君のことなのかシノブ君のことなのか、わからない。
「帰ってこれ、一人で食べるのか。どうしよう」
こちらの言ったことは聞こえていない気配のまま、まだ酔いの残った言葉の断片を残して電話は切れた。
それから冬実の姿を見なくなった。電話も通じずに数日経つ。
「旅行にでも行ったのかも。気まぐれだから」
間々田君は言った。本気でそう思っていそうな能天気さがちょっと怖い。シノブ君も一緒なのだろうか。まさかあの荷物の中に本当に、とは思はないが、彼は今どこにいるのだろう。
行きがかり上、この間のファミレスで間々田君と二人で向き合っている。外は暑そうだが、店内の冷房は寒い。彼は手を組み替えてまた両肘をテーブルにつくと、窓の外を見やり、半分笑顔のまま、寂しげにため息をついた。
ふと、何もかもこの人はわかっているのでは、という疑念が浮かぶ。いや、考えすぎか。ただ、自分でそれと気づかぬまま、皮膚で捉え、皮膚だけで感じるようなやり方で、この人も冬実の「言葉」を受け取っていたのかもしれない。
何だかんだで、自分で選んだわけだよね、この人。でもどうするの。と、ここにはいない冬実に語りかける。
「しょうがないなあ、本当に」
コーヒーを飲み干し、寂しげな笑顔のまま言う間々田君はちょっといい男に見えた。私はなんとなく、冬実が何事もなかったかのように、空のキャリーケースを引いて帰ってくるのではないかという気がした。
※お題「すごいBBQ」で書きました
流れ島流離譚 10
先導してくれるのかと思いきや、ふかふかした腕をしきりに上下に動かし、「どうぞ、どうぞ」と梯子の上を指す。
シマナガシのことだ、半分くらい登ったところで梯子がぐらぐらゆれるだの、上から蛇のおもちゃが落ちてくるだの、幼稚なからくりを仕込んでいるかもしれない。疑いを込めて湿った目つきでじっと見ていると、
「いやだなあ、変ないたずらなんかしませんよ」
妙に大きく明晰に言い切るのだからますます怪しいが、終いには諦めたらしく、
「しょうがないなあ」と梯子を登り始めた。
ぱたん、ぱたん、と長い尻尾を左右に揺らしながらシマナガシの後ろ姿が滑らかに上昇してゆくのも妙な眺めで、普通の猫ならば梯子など登りもしないだろうに、手足の裏側で梯子段を交互にグリップする器用さは、人間同様、どころか人間以上のようなのである。
いつまでも見物していても仕方がないので私も後に続く。
登りきらないうちに何かがおかしいと気がついた。思えば、意識がそれをとらえるのに一歩先んじて、足元をすくわれるような違和感で手足は軽く震え出していた。気づいてみれば、なぜ見えなかったかと首をひねるほど大きなものが、はじめから目の前にあったのだ。
明るすぎる。最初に足を踏み入れた部屋も随分と明るかった。窓は隠れていたが、カーテンを開ければ太陽光が射し込んでくると予測されるには十分だった。あれほど長い階段を降りて着いた先ならば地下のはずなのに、カーテンの後ろに強力な光源でも隠してあるのだろうか。そして、梯子の上から注ぎ込む光は、明らかに階下の光量を上回っており、眩しいほどなのなのだ。
最後の段に手をかけ、一歩を進めるのは怖かった。ちょっと足を踏み外したら落ちてゆきそうな恐怖というものがあるが、今感じているのは、すでに足は踏み外したがいつ落ち始めるかわからない恐怖で、果たして床、つまりは階下にとっての天井から頭を出した瞬間に、恐れていたものは目に入ってしまった。
「ここは地下室だったんじゃ……?」
しばらくの絶句の後、口から出たのはそんな、確かに非常につまらない文言だったが、
「そういうつまらないことを気にしているようでは、いけませんねえ」
わざわざシマナガシに指摘されると腹が立つ。
だが腹を立てているいとまなどなく、とにかく驚くことになるのだ。
向かって右の壁がほぼ全面にわたって窓になっているのだから。そこは島の一方向を見渡せる展望室だった。

流れ島流離譚 9
長い階段だった。
最初は気づかないほどの兆候だった。
それが、一段一段踏みしめるうちに、何かに足を取られる感覚が、いよいよ強くなる。
階段がやわらかな素材に変化したような、地面がゆっくりと揺れているような。
そのうちに、前を歩くシマナガシの後ろ姿が、自分自身の背中に思えてくる。そしてもう一人の自分が後ろからついてくる。私の背中を見つめるそのもう一人の自分も、後ろから誰かに、また別の自分に見つめられている。暗く、長い道である。後ろにもう一人、さらに後ろにもう一人、列を辿ればいつの間にか先頭の私に至る、そんな円環を思わせるほどに。
「胎内めぐりのようでしょう」
振り向かぬまま低く発せられたシマナガシの声が、やけにくぐもって響く。
「思い出して下さい。どうしてハナチャンに出会うことになったのか」
続く厳かな問いかけに、私はさらに深いところへ潜ることで応えようとばかり、記憶の海に頭から飛び込み闇雲に泳ぎ回るも、わからない。なぜ鼻侯爵に出会ったのか。なぜ突然声が聞こえ、この島へやってきたのか。
「そういう時は立ち止まって上を見るんです」
もはや上っているのか下っているのかも曖昧になってきた頃合いのその声は幻聴じみて聞こえた。が、先ほどまで先を歩いていたシマナガシが扉の前で向き直って上を見ている、この景色がほんとうのことならば、言葉もほんとうに違いない。私も上を見上げる。
吸い込まれそうでもあり、すぐに吐き出されそうでもある、半光沢のびろうどの闇があった。首をぐるりと巡らせ、視線を今来た道の方へとやると、薄ぼんやりと光の通路が見える。
視線を戻せば、シマナガシがもう扉へと手をかけている。長い長い階段の、地の底のような果ての部屋へと、到着したようだった。
「ようこそ」
再び、妙なポーズをとるシマナガシを追って一歩踏み入れた部屋の、あまりの明るさに意表をつかれた。
見知らぬ惑星か未来の家のようなドーム状の入り口とは打って変わって、そこはごく普通の部屋だった。クッションの皺や部屋の隅の埃など、ささやかな現実が寄せ集まって持つに至る強烈な日常的存在感は、私が後にしてきたアパートの自室と変わらない、むしろもっと年季を帯びて強固なほどだ。しかしどこか、童話に出てくる「森の中の家」のように抽象的でもある。
壁は明るいクリーム色、窓らしきものがあるが、開口部は空色のカーテンで隠されている。床は若草か苔で覆われているような萌黄色のカーペット。ひょっとしたら本当に草が生えているのかもしれない。
もっとも目を引くのは、入り口の斜め向かいの角にある梯子だった。木製と思しき堅牢そうな造りで壁に固定され、その両端は、天井と床とにそれぞれ開いた穴の向こうへ消えているのだ。
「さあ、やっぱり上から先に見ますか?」
シマナガシが梯子へと一歩近づく。

流れ島流離譚 8

ベリホで上から通信

「新居は階段を千段上る」
Fからの新しいメールにはそう書いてあった。
引っ越すことになりそうだとは聞いていたが、千段というのは普通じゃない。もっとも、普通のメールなんか、来ないのはわかっているのだけれど。
「見晴らしがとてもいいので送ろう」
見晴らしがいいというのか、何というのか。送られてきたのは、画面いっぱい、青い絵の具で塗ったような空が切り取られた写真だった。
私は神社で拾ったそれをベリホと呼んでいる。名づけたのは、友達の弥生だ。スマートフォンよりももっと小さくてスマート、ベリースマートフォンだから、ベリホ、というのが命名の理由で、なるほどとても小さい。学生証くらいのサイズで、もっと薄い。それなのに、ちゃんと光る液晶のような画面がついている。
「いいなあー、ベリホ。わたし、最近ずっと下見て歩いてるけど、ぜんぜん落ちてないよなあ」
弥生は始終うらやむし、珍品であることは認めるが、正直、それほどいいものとも思えない。メールを受信するのだが、文字を入力しての送信はできない。受信しているのも、本当に「メール」と呼んでいいものだか、よくわからない。
最初は、画面に見たことのない模様が現れたのだ。背景は黄色くなったりピンク色になったり、一定しない。その中に、いろいろな長さの細い毛虫かミミズが、丸まったり、反り返ったり、てんでばらばらなポーズを取っているような、変な画像だった。背景の色がどんどん変わるのだから動画なのだろうが、じっと見つめている間は動かない。写真にも、色鉛筆やクレヨンで描いた絵にも見えた。
「外国語?でも英語じゃなさそうだし、漢字とかハングルでもないねえ」
初めて見せた時、弥生が大して驚きもしないことに何より驚いたが、「すぐに戻ってくるから待ってて」と言い残して去るや、三十分もせずに、両手に持てるだけの本を持ってまた登場したのにはもっと驚いた。
「どうしたの、すごい本ね」玄関ですれ違って声をかけたうちの母に「レポートあるから一緒に調べようと思って」と言い訳までして。
ベリホを拾ったことは弥生以外の誰にも言っていない。弥生も誰にも明かしてはいないはずだ。ちょっとずれたところのある子だけれど、そういう、しないほうがよいことへの嗅覚だけは鋭いせいか、友達は少ないのに、嫌われたりいじめられたりもせず、マイペースで好きなことばかりしている。私は弥生の好きなマニアックなゲームだの本だのの話にはまるでついていけないが、何となく弥生の世渡りの流儀みたいなものを真似したおかげで、めんどくさい高校生活をわりと快適に送ってきた。それに、話は合わないけれど気が合うというのか、何だかんだでいつも一緒にいる。
お姉さんに借りてきたという、ありとあらゆる語学や古代文字の本を広げながら、ああだこうだと言い合ううちに、ベリホ画面のミミズ文字は次第にカタカナに、じきに漢字混じりのひらがなに変化した。
「ベリホには人工知能が搭載されていて、わたしたちの会話を聞いて日本語を習得したに違いない」というのがSFやファンタジーをこよなく愛する弥生の解釈で、私は信じ切ってはいないのだが、他に説明もつかないので、そんな気がしてきている。
その後何度も交信するうち、私たちは、悪霊として祓われて閉鎖空間に追いやられようとしていたとある超能力少女のメッセージをキャッチし、彼女を手伝ってひとつのパラレルワールドを救い、その際、弥生のお姉さんである語学マニアの女子大生、朔実さんにだいぶ力を借りたのだが、それはまた別の話だ。
とにかく、この世界ではない可能性の高いどこかからの通信が、時々ベリホにはやってくる。直接出会ったところで言葉も体も違いすぎる存在同士の間を、取り持って通訳してくれる機械らしいのだ。近頃はベリホの日本語もだいぶこなれてきた。
文字で返信はできないが、話しかけると意志が通じることもある。全然通じない場合もある。かと思えば、心で思っただけのはずが伝わってしまうことだってある。魔法のようなベリホだけれど、やはり異界人との交信は難しい。最近の通信相手、つまりFが、人間なのか妖怪なのか宇宙人なのか、まだ全然わかっていない。
「いいよねぇ、異界の人と運命的な出会いとか、あるかもしれないよ」
弥生はベリホに飽きる気配はなく、相変わらず熱い羨望を隠さない。
「まあまあ、しょっちゅう一緒に通信してるんだから、弥生にだって出会いがあるかもしれないじゃん」
「ま、そうだよね」
別にベリホを弥生に譲ってもいいが、こんなふうに機嫌がすぐ直るのだから、興奮しすぎて何か言葉を外に出さないと気が済まないだけなのだろう。むしろ、弥生がはまりすぎると危険なので、渡さないほうが賢明だ。今までのゲームや本の例から身にしみている。それに実は、夜寝る前などに、反応がなくてもベリホに話しかけるのがちょっと楽しくなってきたのも確かだった。
「今度のFって人さあ、なんかちょっと上から目線だよね」
弥生がかすかに不満そうにつぶやく。先日旅に出るからと最後の通信を送ってきた銀河間航空技師の宇宙人のことをやけに気に入っていたから、比較してしまうのだろうか。
「そう?まだまだベリホの翻訳がヘタクソで、変な日本語だからそう見えるだけじゃない」
「うーん、そうかなあ」
こんなやりとりもベリホを通じてFに伝わっているかもしれないことは承知の上だ。何せ反応はたまにしか返ってこない。私たちの通信法が悪いのか、ベリホが怠慢なのか、相手との時間軸が違うのか、さっぱりわからないのだからどんなことでもチャレンジあるのみだ。今日も春休みの1日を全部使う勢いで部屋に引きこもり、通信を試みている。
「Fは山のお寺とかで修行をする人なの?お坊さんとか。お坊さんってわかるかなあ。あのね、わたしたちのところじゃ、階段が千段って、なかなかありえないことなんだよね」
弥生は「千段」をヒントにFの世界に迫ろうとしているようだ。
「あ、それかもしかして、すごく体が大きくて脚が長くて、一歩で千段上れちゃうんじゃない?」
「だったら階段いらないだろ」
「そっか。でもほら、巨人と小人が両方いる世界だとかさ」
「うん、相当な異世界の可能性はあるな。この間の写真からして、空が青く見えるところなのは間違いないけど。おーい、私の身長は155センチくらいだよー。って言っても、センチがわからないかぁ」
その時、2時間くらいは反応がなかったベリホの画面が光り、新しい文字列が表示された。
「階段、千段上るのはたいそう高い位置、千段下りるはたいそう低い位置、それは大変尊敬が大きい」
二人ともしばらく凝視ののち沈黙してしまうのはよくあることだ。
「尊敬されるところに住みたいから階段千段の家に引っ越したってこと?上から目線ていうか、単に変なやつだなこいつ」
弥生は壊れたロボットみたいに何度も頷いてにやにやしている。続いてまた画面が光った。
「わたくしに敬意を払ってわたくしの子が作ってくれたのだこの新しい建造物を」
「えー、Fって子供いるんだ。けっこうおじさん?それかおばさんか」
Fと弥生の会話が盛り上がってきている。会話、といっていいくらい通信が続くことも、今のように時々あるのだ。日本語が急に上達するなど、ベリホが大きくバージョンアップした時に多い。
「おじさんおばさんのこと、その種類はわたくしと大変遠い。しかしわたくしの子、おじさんと近い」
「うーんと、Fはおじさんでもおばさんでもないけど、子供はおじさんに近いと。息子なんだ?」
「おじさんやおばさんを超越した年齢ってことかな、それとも、性別が3種類以上ある世界だとか」
「3という数、衛星を意味するのことがある、弥生、関係する、今の時間」
ベリホの日本語が上達したとはいえ、やはりFの言葉の多くは意味不明だ。だが、あることがひらめいた。
「あれ、衛星って、月のことでしょ。これってもしかして、弥生の生まれたのが3月かって聞いてない?」
「おおっ、誕生日のこと聞いてくれてる?」
すぐに返信が来た。
「誕生日、あなたのところ、生きている人はよろこぶ。生きていない人はわからない。わたくしたち、生きてない人の誕生日、よろこばせない」
「また、よくわからないことを。Fの世界では、死んじゃった人の誕生日はお祝いしないってことかな」
「それ正確な意味。お祝い、祝福、しない。死んだ人、忘れられないが、お祝い、しない」
画面の背景が心なしか暗くなり、Fが沈んでいるように感じられる。
「弥生、もしかして、Fってもう死んじゃった人なんじゃない」
生まれるとか死ぬとか、そういうこともない世界なのかもしれないのに、なぜかそんな気がした。
「そうかも。わたしたちは、今日は死んだおばあちゃんの誕生日だなあとか思うけど、Fのところは違うのかな。それとも、もっと盛大に祝ってほしいのかな。とにかく誕生日のお祝いしてもらえなくてさびしいんだ。誕生日、いつなの?」
「四つ目と五つ目の衛星の二番目に交わってから三周回」
弥生の問いかけは的確だったようだが、答は私たちの理解を超えている。
「あーだめだ、異世界過ぎてわからない。それよりもしかしてFの新居って……お墓?」
「新居ってことは、亡くなったばっかりなのかな。階段が千段もあるお墓を、息子が作ってくれたってこと?」
Fが黙り込んだ。
正確には、ベリホの反応が途切れたということだけれど、私たちは何やらしんみりしてしまう。が、数分後にまたベリホが光った。
「お墓と家とは同じもの。わたくしは死んでからも同じ家にいたけれどわたくしの子が新しい家を建設してくれた」
「ふーん、新しいお墓を建ててくれたんだ。親孝行だねえ」
「誕生日も祝ってくれたらいいのにね」
やはり少し自慢げな上から目線は見逃して弥生も私もいつしかFを慰めるような口調になっていたが、
「いや、ちょっと待て。階段が千段ある墓って何だ、ピラミッド?」
「もしかしてFってすごく地位の高い人?ファラオとか」
二人、息をのむ。
「わたくしの子が王位を継いだ時から秘密の建設がはじまっていた。新しい家、わたくしの子からのサプライズ」
「あー、ほんとに王かよ」
「セレブだね」
「上から目線のはずだよ。もういいじゃん、死んでも尊敬されてるんだから誕生日とかどうでも」
「ところで弥生、なんで誕生日だとかサプライズだとかいう概念がFに伝わってたんだと思う?」
「ベリホのやつ賢いからなあ」
弥生はベリホを放り出して寝転んだ。鈍いところはとことん鈍い子だ。
「ちょっと早いけど、誕生日おめでとう!最近私が散々サプライズだとかプレゼントだとか、ぶつぶつ話しかけてたからだと思うんだよね。はい、これあげる」
私はここしばらく悩み抜いて選んだプレゼントを差し出した。誕生日は明日だけれど、この状況で今渡したくなったのだ。
「え、何それすごく嬉しいんだけど!見てもいい?」
目を輝かせて早速ラッピングを解こうとしている弥生にふと話しかける。
「Fってちょっと変だけどいい人だと思うよ。弥生の誕生日どうしようってしゃべってた時、メールは来なかったけど、時々画面が光ったり、色が変わったりしてたんだ。きっとさ、プレゼント何がいいとかいう相談にはわからなすぎて乗れないけど、はげましてくれてたんだよ」
「それで生きてた時の誕生日のこととか、思い出しちゃったのかな。そっか、ごめんねF。誕生日の時は教えてよ、三日前くらいにさ」
またしんみりする私たちなのだった。いつか生きることが終わって、弥生も私もどこか別の世界に引っ越すのだろうか。階段が千段もなくてもいいけど、誕生日の思い出を持って行けるなら、悪くない。それに、持って行けなくても、今日という日がなくなるわけじゃないのだから、いいのかもしれない。
「あ、メール来た」
弥生が手を止めてベリホをつかむ。
「弥生、わたくしからも誕生日の祝福を与えよう」
満天の星空が送られてきた。
「ほんとに上から目線だな」
「いやでも、星空は下から見上げるものだよ?」
と、同感だったが一応フォローしておく。
「宇宙の彼方からこっちを見上げたら、見下ろしてるのと同じでしょ」
「じゃあ向こうから見たら、私たちのほうが上から目線かもね」
「あははは、確かに」
プレゼントを開ける手が、あと少しのところでまたもどかしく止まるのだった。
お題「引っ越し」で書きました