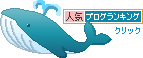流れ島流離譚 6
鼻侯爵に会った頃、私は毎日、仕事からの帰路を誰かにつけられていた。
その時は、家も間近な、しかし最も暗い道にさしかかっていた。びくびくしながら、ポケットの中の防犯ブザーに手をかけ、早足で道を急いでいたところ、行く手を大きな影が塞いだ。つけてくる気配を背後に感じていたのだから、ワープか、挟み撃ちか、と恐怖も倍増するというものだ。だが、やはり声などは出なかった。
だいたい、現れたものが想定の外の外、大きな猫だったのだ。頭に毛糸で編んだベレー帽をかぶっていた。帽子の真ん中のへそのような部分、つまり頭頂部からは、茎が伸びていて、その先に花が咲いていた。花の種類はよくわからないが、コスモスやガーベラのように平べったい、オレンジ色の花だったと思う。
「それにしても簡単な手にだまされましたね。なに、単純な原理の幻燈機ですよ」
シマナガシの声で我にかえる。見知らぬ巨大猫と相対しているのはあの時と同じだが、人間、慣れるもので、もはや違和感がないことが恐ろしい。
シマナガシがしゃがみこんで拾った落し物は、やや大きめの懐中電灯だろうか。それと、セロハンの切れ端と思しき物が何枚か。
なるほど、木の幹に映った顔の正体だ。こんな仕掛けに驚いた私も私だが、幼稚ないたずらにもほどがある。私がここへ来ることがわかっていて、あらかじめ作ってあったのか。それとも日頃からこんなもので遊んでいるのか。子供か。だいたいこれは「幻燈機」というほどのものなのか。私は騙されそうにはなったが見破ったのだ。
チェシャ猫のことを「知恵者猫」だと思っていた子供の頃をふと思い出し、こんなのをチェシャ猫のようだと思ってしまった不覚を恥じた。
「話の続きがまだですよ、何なんです、ハナコーシャクって」
シマナガシはまた両手を腰に当てて期待にみちた目で見ている。案外としつこい。
「本当に知らないんですか。あなたと同じくらいの大きさの、言葉を話す猫なんですが」
「何をそんなに疑っているんです。お互い腹を割って話しましょうよ、女同士」
こいつ女だったのか、と思うや否や、シマナガシはニャッ、と鳴き、「今、同じことをあなたに対して思った人が5人くらいはいますね」と、気味の悪いことを言った。
「心が読めるんですか。それに5人ってどういうことです、このへんに他にも誰か」
「いやなに、初歩的な推理ですよ」
あくまでもシャーロック・ホームズ気取りで答をはぐらかす気だ。島流しにしてくれよう、と言った声と頭の中で照合するも、まったく違う気がする。
「じゃあ、お茶でも飲みながら話しましょうか」
シマナガシは歩きはじめた。