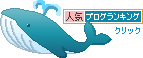流れ島流離譚 11
自分の住む世界のすべてを客観的に見通したければ高いところへのぼればいい。町外れの丘、町で一番高い塔。そんなものがなければ、飛行機に乗るなり、翼をつけてジャンプするなりどうにかして。
確かそんなことを鼻侯爵が言っていた。
「ジャンプするっていうのは、無理があるな」
思わず口に出せば、
「ほほう、飛び降りますか、ここから」
と、とんちんかんな答えをくれるのはもちろんシマナガシで、約束通りお茶を入れてもらい、いつしか語り合っている。
窓の外は笑ってしまうような景色である。「絵葉書のような」という表現があるが、絵葉書の絶景を真似て子供が7色くらいのクレヨンで描いたような、異様に鮮やかな景色がここにある。青緑色の色合いを微妙に変えながら水平線まで続く海、そのぼやけた境界から湧き出す雲を纏った空。それらを遠景に、この島のくっきりとした陰影のある青い森、白茶色の崖、白亜の砂浜。そしてこの部屋は、テーブルといい椅子といい、目に入る調度のほとんどが、ガラスだろうか、無色透明にできている。透き通ったティーポットから透き通ったカップに注がれた薄黄色のお茶をごくりと飲む。初夏の花の香りがする。
「高いところに、ねえ。そうとも言えるしそうでないとも言えましょう。低いところへ行ってもよければ、高くも低くもないところもまたよし。そうですよねえ」
シマナガシの意味不明の相槌は鼻侯爵の不敵に謎めかせた話し方を思わせて、今の今まで忘れていた記憶の断片が次々と顔を出して私を混乱させる。
「そうだ、でも、高いところへのぼればそれでいいと思ってはいけない、とも言っていた」
「ほほう」
「高いところからはたくさんのものが見えるけれど、たとえば入ったことのない隣家の風呂場からの眺めを知ることはできない。自分の家の窓から見えるもの以外はほとんど見えはしない、ただほんの少しずつすべてがずれて見えるその眺めがどんな感覚をもたらすか、町を俯瞰したくらいで決してわかりはしない。確か、そんなようなことを」
「なるほど、やっぱりね。そんな単純なやつじゃないと思いましたよ、ハナチャンは」
シマナガシは満足そうに顎を撫でている。さっきから、何も言っていないに等しい適当なことばかり言うのだから、少々腹も立ってこようというものだが、
「いやなに、実に初歩的な推理をしただけですよ」
と、何を誤解したのかまたホームズ気取りなのである。
「つかぬことを聞くけれど、猫って肩、凝る?」
突然話題を変えてみると、シマナガシは丸い翡翠のような目をさらに大きく見開き、ぱちぱちと瞬きをした。