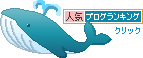流れ島流離譚 2
あたたかく湿り気のある風が頬にかかり、助かった、南の島だ、という安堵で、知らず知らずのうちに緊張で固まっていたらしい体がふっとゆるむ。
何しろ寒がりである。氷に閉ざされた極域の島になど送られたらどうするつもりだったのか、今さら自分の向こう見ずに呆れるばかりだ。
目の前が青一色である。海だろうか、いや、空の色だ。壁に寄りかかって上を向いていたことに気づく。よく見れば人工の壁ではなく、そう高くはない崖だった。足元には流木だの海藻だのがごちゃごちゃと積み上がっており、漂流物の吹きだまりのような場所らしい。私も漂流物のひとつというわけだろう。
次第に周囲が明瞭に見えてくる。砂浜の上、入り江のように低い崖に囲まれたのがこの吹きだまりだったようで、風の吹く方へ少し歩みをすすめれば、すぐに砂浜の果て、そしてその先の海が見えた。写真でしか見たことのない、エメラルドグリーンの南の海。どんな危険な猛獣やら毒虫やらがいるかもしれないぞ、と自分をつい抑えてしまうのは、むしろ愉快なところへ来たという喜びで浮かれているからに違いない。
なかなか粋な計らいじゃないか、とわざとらしく芝居がかった台詞を言ってみた、正確には心の中で思ってみたのは、またあの声が聞こえるかどうかを確かめるためでもあったのだが、何も聞こえてこない。安心したような拍子抜けのような心持ちである。
その時、さっと視界の隅を影が走った。海の方から先ほどの吹きだまりの方向へ、誰かが走り去ったようだった。
「鼻侯爵」
と、私はつい叫んで走り出していた。
知り合いにひどく似ていたのである。一瞬見ただけの影で「似ている」と判じるからには、尋常一様でない特徴がもちろんあったのだ。その人影にも、鼻侯爵にも。
走るのが異様に速いということもある。だがもっと大きな特徴は、それが「人影」ではなく実は「猫影」であったこと、しかも人間ほどの大きさで、二足歩行する猫の姿であったことだ。
「おーい」
声を出しながらもといた辺りまで追いかけるが、もう誰もいない。少し後ずさりして崖の上を見渡してみるも、容赦なくもじゃもじゃと茂った木々の葉に遮られて、何も見えない。
鼻侯爵、どこへ行った。
すっかり怪しい人影、ならぬ猫影の正体であると決めつけている「鼻侯爵」こそ、何を隠そう、私が人生でめぐりあった、二つ目くらいの怪異なのだ。