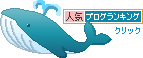カスタードプリンのかなしみ

ここが嫌いなわけじゃない。
ただ、決定的に欠けているものがひとつだけある。それは、命と同じくらい大事なものなんだ。
少年はそう言ってうつむいた。
「花粉症っていうけどさ、私あれ、違うと思うんだ」
「花粉が原因じゃないとかそういうこと?」
「違う、違う。花粉症が辛いっていうけど、ほんとに辛いのはお前じゃないだろうって話よ」
「ええ〜?何言ってんの、だってめちゃくちゃ辛いでしょ。一日中ムズムズするし頭ぼんやりするし、もう春なんか来なくていいって思うくらいだよ。それにさ」
「落ち着け、わかるよ。私だって花粉症だ」
「あ、そうだよね」
「花粉症、って世の中で呼ばれているやつ、ってことだけどね、あくまでも」
「あーはいはい、それで」
花を咲かせて、果実を実らせないと生まれてきた甲斐がないとか、そういうのも別にないんだ。
変だと思う?そうかな、けっこうみんな、そうだと思うけど。
生き物として不自然じゃないかって?本能はどうしたって?
だからね、生まれてきた以上子孫を残さないといけないっていうのは、じぶんの気持ちじゃなくて、言ってみれば遺伝子の気持ちだと思うんだ。別の言い方をすれば、競い合って殺し合っても誰かが生き残れ我が遺伝子よ、って命じて死んじゃった、遠いご先祖さまの気持ち。そうそう、君らと僕らの共通のご先祖ね。ちょっと迷惑なやつだよね。きょうだい同士殺し合って強くなるのを見て喜んでる親って。
そういうのから自由に生きたいんだ。君らの世の中でも、同じこと思う人、いるんじゃないかな。
「だからさ、人の鼻の中だの目の中だのに入っちゃった花粉の方がよっぽど辛いじゃん」
「でも、花粉なんて辛いとか、思わないでしょ」
「なんでわかるんだよなんでなんで!花粉になったことあるのかよ」
「ないけどさ……まあ興奮しないでよ」
「花粉はさ、花のめしべまで行くために飛んでるわけじゃん。受粉して、実がなって、種ができて、っていうのがないと、絶滅しちゃうじゃん」
「そういえばそうだよねえ、確かに」
「それがさ、何が悲しくて人間の鼻の中に入っちゃってさ、鼻水と一緒にティッシュの中に出されて丸めてポイって!」
「うんうん、そうだねそうだね。ほらでも、花粉ってすごくいっぱいあるでしょ。いっぱいあるうちのどれかが受粉できればOKっていう、何ていうの、自然界の掟っていうか、数で勝負の戦略っていうか」
誰かがそういう役割をすれば十分だと思うんだ。一度に一億個の卵を生む魚がいるの、知ってるよね。あれだって、成長する途中でほとんど死んじゃうのも仕方なし、ってことだよね。逆に全部が成長したら大変なことになる。
それに僕の場合、他のやつらより早く死ぬってわけじゃないんだし、流れ着いたところで、自分らしくいられれば満足だよ。
誰かが子孫を残す役割をすればいい、って言ったけど、誰もしなくてもそれはそれでありだと思う。滅び去るのも自然なことだから。みんながしたがって競争したとしても、いいと思うよ。そういうの、否定したいわけじゃない。自分は自分だってだけ。
「そういうこと言い出したら、人間だって、ちょっとくらい死んだって全体としては問題ない、食料足りてないんだしかえってラッキー、みたいなこと言うのと同じでしょ」
「そうかなあ」
「ひとつぶひとつぶの花粉の身にもなってごらんよ、泣いてるんだよ花粉が」
「花粉は目とかないから泣かないんじゃ」
「そういうことじゃないってば。人間はかゆいくらいで済むけど、花粉は人生かかってるんだから。花粉症っていうのは、だから、花粉が人間に取り込まれちゃって悲しんでて、それで起こる症状だと思うわけ」
「花粉が泣くと、人間の鼻とか目がかゆくなったりする、と」
「そうそう。花粉が人間症にかかってるんだよ」
「あー、発想の転換てやつだね」
「わかってくれたか」
「あれ?でもさ、それ変だよ。だって、花粉症じゃない人がなんでいるの。花粉にとっては、誰の鼻の中に入ったって同じことじゃん」
暖かくて、薄暗くて、湿ったところ、好きだし。そんなに居心地悪くないよ、ここ。
どこにいても、その場所で精一杯楽しもうって覚悟してる、最初から。だから十分すぎるくらい。
「そう、ここからが問題なんだよ」
「えっ、まだ続きあるの?」
「花粉のひとつぶひとつぶはさ、別に花のめしべに届くために生きてるわけじゃないと思うんだ」
「花粉は生きてるのかってのも微妙だし、さっきの話と違うのでは」
「いいからいいから。さっきのは、話をわかりやすくしようとしただけ。風に任せて飛んでいって、たどり着いた新天地でがんばろうっていうのが花粉の基本的な生き方なわけさ」
「うーん、そうかもね。羽とか足とか、ないからね」
「だから、どんな場所にでもそれなりになじんで、うまくやるはずなんだ」
「人間も、与えられた環境でできるだけがんばるしかないもんね」
「そうだよ。でもやっぱりさ、人間だって、これだけは譲れないってものが、あるだろ」
「えっ、あんたそんなのあるの?何?」
「いや、何だかまではわからないけど、あるんじゃないかなあって」
「そういうことか。あるのかなあ。『生きがい』みたいなやつのこと?」
「わからん。でもあるのかも」
「あるのかもねえ」
「そう思うでしょ」
「で、花粉はどうした」
「花粉にとっても、大事な、譲れない『何か』があって、それが足りないんだと思う、花粉症の人の体の中には」
「だから花粉が泣いて、花粉症になるってこと?」
「うん、まあほんとは、花粉の人間症なんだけどね」
わかってもらえるといいんだけど。
ここが嫌いとか不満とか、そういうことじゃないんだよ。
でも……。
彼は空を懐かしむように上を見上げて一粒涙をこぼすと、それきり何も言わなくなった。
「私たち、何かが足りないんだ」
「足りないんだよ、悲しいよね」
「悲しいねえ。って、そんなわけあるかよ!……まあでもそこまで言うなら、何が足りないのか考えなよ」
「ひとまず、プリンじゃないかと思うので試してみたい」
「それ賛成。ひょっとしてプリンが食べたくて今の話」
「違うよ、全然違う」
「他にも色々食べたいんだな、さては」
「食欲の春だからね」
「だね」
彼が何を欲しがっていたのかは結局わからなかった。私が何をしたかったのかも本当はわからない。ただ、少年の体といい髪といい、そして涙といい、透明感のある美しいクリーム色だったのだ。
ちょうどカスタードプリンのような。
お題「花粉症」で書きました
流れ島流離譚 7

流れ島流離譚 6

流れ島流離譚 5

流れ島流離譚 4

百年の読書
百年という名の書店に行った。
吉祥寺にある古書店であるが、久々の古書店の雰囲気がとても心地よかった。
本がたくさんあるのは嬉しい。本が大好きだ。世の中にこんなにもたくさんの本がまだあるかと思うとぞくぞくしてくる。そんな感覚が、実に久しぶりだった。
というのも、うちの近所では古書店が続々と閉店しているし、新刊書店は、「すごく売れている本」に割くスペースばかりが年々増えていく印象だ。
売れているからだめなどとは思わない。多くの人が求めているからにはその本に何かしら特別さがあるのだろう、と手に取ったりもする。ぱらぱらと読んでみて、自分なりにその「特別さ」を見つけ出してみる。それは面白い体験だ。
そういう時、自分ではないバーチャル別人視点、のようなものを装着していると思う。実際のところそれは自分でしかないのだけれど、ちょっと自分自身から離れた視点を持つのは大事なことだ。そう感じるからこそ本屋さんで特に心がときめくわけではない本を手に取ってみたりもするのだが、その「バーチャル視点」、装着しっぱなしは疲れる。非常に疲れる。でも、思ったほど自由自在には着脱できないようなのだ。
店主の確かな趣味で集められた古書の林に分け入った時、バーチャル別人視点がぽろぽろと落ち、本を読みたい!本大好き!というネイティブ・自分の煩悩が解放される心地がしたのであった。
単にその書店の趣味が私の趣味に一致したということでは、必ずしもない。もちろん、趣味のかぶる部分の割合が一定以上あったのは間違いない。だがそれよりも、ありがちな言い方ではあるけれど、大多数の行く方についていくのではないあり方を、「本」の世界で久しぶりに見たように感じたのだ。しかも、こうありたいという言葉だけではなく、静かに実践する姿として、とても強く。
本が売れないとか本を読む人が減ったとか言われているし、紙の本はこれからまた衰退の道を辿るのかもしれない。でも、人が「読む」「見る」コンテンツを求めていないわけではない。そう思えて仕方がないのは自分が旧人類だからなんだろうか。
ともかく、バーチャル別人視点を極力装着しないで自由に書きたい、考えたことも、自分が本当に読みたいものも。ここで非常に匿名性の高いやり方で、知り合いには誰にも教えずにひっそりと書き始めることにしたのも、そういう欲求のさせたことだったと思う。
というわけで、これを何かの偶然で読んで下さった、袖擦り合ったご縁のある方、どうぞよろしくお願いします。
それでは、また。
流れ島流離譚 3