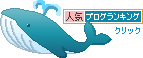流れ島流離譚 3
とにかく、鼻侯爵を追うことにする。
肩を組んで見下ろす巨人たちのような崖は、さすがによじ登るには厳しそうで、とかげや虫なら楽々と登るだろうなあ、とあまり役にも立たない想像をする。正確には、人間であっても身が軽ければ登れる高さだろうが、私の運動神経では絶望する他ない。
ふと思い至り、周囲をきょろきょろ見回す。
では、とかげにしてくれようか、という声が聞こえてきはしないかと気になったからで、まだこの世界への信頼とでもいうものに圧倒的に欠けているのだった。立っていて爪先がむずむずと落ち着かないのも、足元の何の変哲もない土にさえ欺かれている気がするからだろうか。しかしこの座りの悪さには覚えがある。船上にいる時の感覚ではないだろうか。そういえば、先ほどから地面がわずかに揺れてはいないか。
試みに吹きだまりを脱し、陸地の果てと遠くの海とを見比べる。息をひそめ、身じろぎもせずに。ひどく静かだ。海も静かならば島も静かで、揺れている気配はない。
いったいここはどこなんだろう。私は何をしているのか。
じっとしていると、これまで考えずにいたことが頭の中を占拠しようとするのだが、そんなことより鼻侯爵だ。考える暇なら後で売りたいほどにできるだろう。土産物でふくらんだ旅の荷物をスーツケースに押し込むように、終わりのない問いかけを頭の中にしまう。
吹きだまりの壁となっていた崖を改めて外から眺めると、なんのことはない、切り立って見えたのは中からだけのことで、ゆるやかなスロープ状の斜面に導かれて簡単に回り込むことができそうなのだった。
「おーい、鼻侯爵」
斜面を一歩上るごとに、すぐ目の前にせり出してくる枝だの葉だのの数が増える。が、けもの道すらない森の中とはこういうものかと、のんきに感心しながら踏みしめる足元は、意外なほど平坦で歩きやすく、無心に足を動かしていると、ここがどこかなど、次第に気にならなくなってきた。先ほど吹きだまりから見上げた辺りにたどり着く。崖下のほうを見れば、砂浜、海、海、あとは水平線までひたすら海である。逆へ振り返ると、下から見たほど鬱蒼とした密林ではなく、まだ上り坂が続くものの、それもあと少しで果てそうだとわかるくらいの見通しがある。
「おーい、ハナちゃーん」
これは鼻侯爵がひどく嫌がる呼び方だった。人間くさいところが多々あったが、気にそまない呼び名に対する迷惑そうな表情は猫そのもので、思い出すだけでおかしくなる。
「ハナちゃーん、出ておいで」
その時、後ろでがさごそと音がした。はっとして振り向いたとたん私は凍りついた。
目の前の、大きな葉を茂らせた芭蕉のような木の幹に、大きな猫の顔が浮かび上がり、またすぐに消えたのだ。