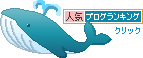流れ島流離譚 4
本当に驚いた時には声など出ないというが、その時の私は、声のかたまりが喉に詰まって息ができないのに近かった。
目の前の木の幹に浮かんだ猫の顔が消えたかと思うと、今度は隣、そのまた隣の木に。そして、『ふしぎの国のアリス』のチェシャ猫のように、笑いながら消えてゆく。といっても、猫の表情までつぶさに見えたとは考えにくい。笑った気がしただけかもしれない。
この後、どんなことが起こるのだろうか。島流しにありそうな災厄として、海に落ちるだの、穴に落ちるだのの他に、蛇に噛まれる、食べ物がない、あたりまでは想像できたが、そういう種類のことではないのかもしれない。やはり、とんでもないところへ来てしまったようだ。
一方、驚きながらもどこかに違和感を覚えていた。
猫の顔は十歩ほど先の木の幹まで移動したかと思うと、またすぐ近くの木へと近づいてくる。私は敵の分身の術を見破ろうとする剣豪のようなポーズで聴覚に集中した。猫の顔からは音がしない。運動神経などあってないような私だが、これでも耳は良いのだ。
そして、見破った。静寂の中、唯一といっていいほどの微かな音が、猫の顔が島の深部へいざなうように連続して現れた方向とは違う、崖に沿って再び海岸へと下りてゆく方からするという、違和感の正体を。
まっすぐ歩いてゆくと、音の発信源が、諦めたのか自ら木の陰から出てきた。
「こんにちは。驚きました?」
両手を後ろ手ににじり出て、とぼけた調子で話すそれは、やはり二足歩行する超大型の猫であった。灰茶色に黒い縞のある、やや毛の長い猫である。鼻侯爵はグレー一色の短く密な毛で被われた猫だから、別人、ならぬ別猫のように見える。だが、人を驚かすためとあらば毛を縞模様にでも染めかねないあの性格を鑑みるに、この人騒がせな猫が鼻侯爵でないと断言できるだろうか。
「さっきから何なんです、ハナコーシャクだのハナチャンだのって」
猫がハナ、と発音する度に、鼻の上にしわを寄せるのがおかしい。鼻侯爵にもこんな癖があっただろうか。
「確かにもようが違うけれど、本当に鼻侯爵じゃないの?」
疑いのたっぷりこもった目でじろじろ見ながら言うと、猫は美しい青緑色の瞳で見つめ返す。
「だから何それ。食べられるの?」
どうも本当に別猫らしいのだった。