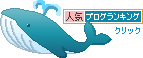流れ島流離譚 9
長い階段だった。
最初は気づかないほどの兆候だった。
それが、一段一段踏みしめるうちに、何かに足を取られる感覚が、いよいよ強くなる。
階段がやわらかな素材に変化したような、地面がゆっくりと揺れているような。
そのうちに、前を歩くシマナガシの後ろ姿が、自分自身の背中に思えてくる。そしてもう一人の自分が後ろからついてくる。私の背中を見つめるそのもう一人の自分も、後ろから誰かに、また別の自分に見つめられている。暗く、長い道である。後ろにもう一人、さらに後ろにもう一人、列を辿ればいつの間にか先頭の私に至る、そんな円環を思わせるほどに。
「胎内めぐりのようでしょう」
振り向かぬまま低く発せられたシマナガシの声が、やけにくぐもって響く。
「思い出して下さい。どうしてハナチャンに出会うことになったのか」
続く厳かな問いかけに、私はさらに深いところへ潜ることで応えようとばかり、記憶の海に頭から飛び込み闇雲に泳ぎ回るも、わからない。なぜ鼻侯爵に出会ったのか。なぜ突然声が聞こえ、この島へやってきたのか。
「そういう時は立ち止まって上を見るんです」
もはや上っているのか下っているのかも曖昧になってきた頃合いのその声は幻聴じみて聞こえた。が、先ほどまで先を歩いていたシマナガシが扉の前で向き直って上を見ている、この景色がほんとうのことならば、言葉もほんとうに違いない。私も上を見上げる。
吸い込まれそうでもあり、すぐに吐き出されそうでもある、半光沢のびろうどの闇があった。首をぐるりと巡らせ、視線を今来た道の方へとやると、薄ぼんやりと光の通路が見える。
視線を戻せば、シマナガシがもう扉へと手をかけている。長い長い階段の、地の底のような果ての部屋へと、到着したようだった。
「ようこそ」
再び、妙なポーズをとるシマナガシを追って一歩踏み入れた部屋の、あまりの明るさに意表をつかれた。
見知らぬ惑星か未来の家のようなドーム状の入り口とは打って変わって、そこはごく普通の部屋だった。クッションの皺や部屋の隅の埃など、ささやかな現実が寄せ集まって持つに至る強烈な日常的存在感は、私が後にしてきたアパートの自室と変わらない、むしろもっと年季を帯びて強固なほどだ。しかしどこか、童話に出てくる「森の中の家」のように抽象的でもある。
壁は明るいクリーム色、窓らしきものがあるが、開口部は空色のカーテンで隠されている。床は若草か苔で覆われているような萌黄色のカーペット。ひょっとしたら本当に草が生えているのかもしれない。
もっとも目を引くのは、入り口の斜め向かいの角にある梯子だった。木製と思しき堅牢そうな造りで壁に固定され、その両端は、天井と床とにそれぞれ開いた穴の向こうへ消えているのだ。
「さあ、やっぱり上から先に見ますか?」
シマナガシが梯子へと一歩近づく。